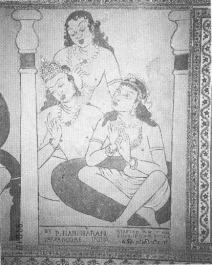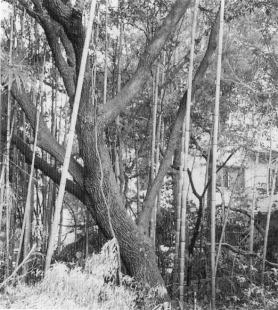「揚輝荘」は、松坂屋の初代社長、伊藤次郎左衛門祐民(すけたみ)氏によって、覚王山日泰寺の東南に隣接する1万坪の森を拓いて築かれた別荘です。完成時(昭和12年頃)には、広大な庭園の中に30数棟の移築・新築された各種建造物が立ち並び、覚王山の高台に威容を誇っていました。観月の茶室「峠の茶屋」、徳川家から移築した貴賓館「有芳軒(ゆうほうけん)」、大石蔵之助ゆかりの「端の寮」、500年前の民家「栗廼家(くりのや)」、八丈島の「四阿(あずまや)」等々、どれ一つをとっても建築的・歴史的な興味が尽きないものばかりで、現在の明治村にも比肩され、「普請道楽」といわれた施主の面目躍如たるものがあります。
ここには、戦前から皇族や、政・官・財・軍の要人が往来し、社交サロンとして賑わっていました。また、祐民氏の支援により、アジアの留学生が寄宿生活を送り、国際的なコミュニティーを形成しておりました。
ところが、1945年(昭和20)3月24日の大空襲では敷地内に15発もの爆弾が投下され、無残にもほとんどの建物が破壊されてしまいました。その夜、ここの住人たちは、トンネルに逃げ込み、危うく難を逃れましたが、翌朝、一望の焼け野原に、息をのんだということです。
そんな災難の中でも、山荘「聴松閣(ちょうしょうかく)」、川上貞奴が住んでいた「揚輝荘座敷」、尾張徳川家から移築した和室に鈴木禎次氏設計の洋間を組み合わせた「伴華楼(ぱんがろう)」などが奇跡的に助かったのは幸運なことでした。
その後、残された建物は、進駐軍の接収を受けたり、松坂屋の独身寮になったりして数奇な運命を辿りましたが、優雅な庭園とともに今なお、その魅力は人々の心を引きつけて止みません。困難な状況を乗り越え、ここまで保持されてきた現在の「揚輝荘」は、大正・昭和時代を生きぬいてきた証人であり、この地域の文化資産として長く保存・活用されるべきものでしょう。